東南アジアを知る 鶴見良行 岩波新書 ★★★☆☆
序盤は訳がわからないが、読み進めていくうちにだんだん面白くなってくる。バナナ、ナマコ、エビなどの話は具体性があって面白い。
改めて東南アジアの地図を眺めてみると、実にたくさんの島がある。その一つ一つに独自の文化があると思うと、眩暈がする。そういう小さな島々を、丹念に旅してみたいものだ。
この本がどういうものであるかは、最後の最後まで読み進めてやっとわかる。
この本は鶴見良行本人が書いたものではない。1994年に著者が急逝したのち、弟子が講演会の講義録をまとめたものなのだ。
著者は大正15年生まれだから、思いっきり戦中派である。40歳にして初めて外国の地を踏んだ。アメリカ行きの途上に立ち寄ったサイゴンで、ベトコンの公開処刑を見たのが、東南アジアについて考え始めるきっかけだったという。
そして、50歳を過ぎてから、東南アジアの辺境を歩いては本を執筆するという「辺境学」「歩く学問」のスタイルを確立させた。このことは、50代になっても人は新しいことができるのだ、という希望を与えてくれる。
一方で、大学を権威主義的として否定し、在野で研究するというスタンスは、日本が豊かだった1980〜90年代だったからこそできたという気がする。今の若者には共感されないだろう。
まずは、名著との誉れ高い『バナナと日本人』を読んでみようと思う。(20/09/26読了 21/01/28更新)
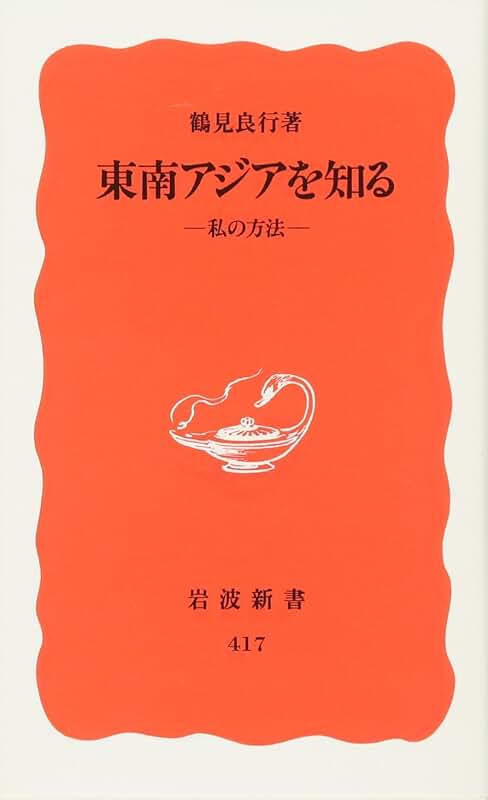
 読書日記 2020年
読書日記 2020年 